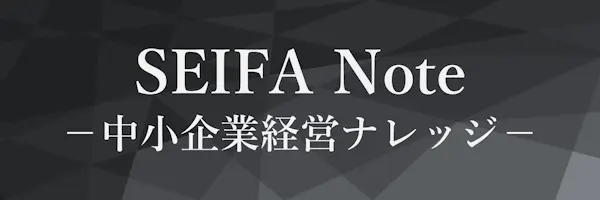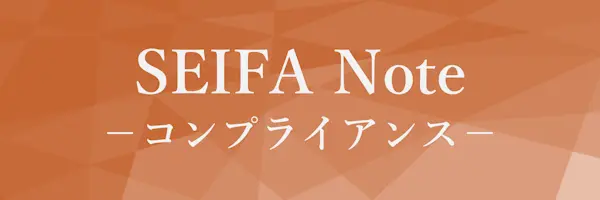ゼロトラストとは?現代のセキュリティに求められる新たな常識
最終更新日:2025/04/07
あなたの会社のデータ、あなたの使っているスマートフォン、日々やり取りしているメールなど、これらがすべてが、「いつでもどこからでも狙われる時代」にあります。
昔は「社内のネットワークにいれば安心」と考えられてきましたが、今はテレワークやクラウドサービスの普及により、その安心の壁はなくなりつつあります。
そんな現代の働き方・暮らし方に合わせて注目されているのが、「ゼロトラスト」というセキュリティの考え方です。
今回は、専門知識がなくてもわかるように、ゼロトラストとは何か、なぜ必要なのか、そしてどう活かせるのかを解説します。
これからの時代を安全に、そして安心して生きていくための“新しい常識”を一緒に学んでいきましょう。
第1章|なぜセキュリティ対策が今、注目されているのか?

今や、仕事でも学校でも、スマートフォンやパソコン、インターネットが欠かせない時代です。
ファイルはクラウドに保存し、会議はオンライン、資料もチャットで共有するといった働き方や学び方が当たり前になりました。
便利になった一方で、それに合わせて「サイバー攻撃」や「情報漏えい」のリスクも急増しています。
しかも攻撃の対象は、大企業だけではありません。
中小企業や学校、個人にまで広がっていて、「まさか自分が」、「うちの会社は関係ない」とは言い切れない時代になっています。
例えば、「社員の1人がうっかり怪しいリンクをクリックした」、「外出先で使っていたノートパソコンが盗まれた」、「パスワードが簡単すぎて他人に破られてしまった」など、ちょっとしたスキから、大切な情報が外に漏れたり、業務が止まってしまったりすることもあります。
だからこそ、今、どんな企業や組織も「セキュリティ対策」を真剣に考えなければいけません。
その中でも特に注目されているのが、「誰も最初からは信じない」という前提で守る「ゼロトラスト」という考え方です。
第2章|ゼロトラストとは?「誰も信じない」新しいセキュリティの考え方

「ゼロトラスト」とは、簡単に言うと、誰であっても最初から信頼せず、すべてのアクセスをしっかり確認するという考え方です。
これまでのセキュリティは、「一度ログインしたら社内ネットワークは安全」、「信頼された人だけが入れるから安心」という前提で動いていました。
でも今は、社内・社外という境界があいまいになり、社員でも外部からアクセスするのが当たり前の時代です。
だからこそゼロトラストでは、こう考えます。
「たとえ社員でも、毎回ちゃんと本人確認しよう」
「使っている端末は本当に安全?それもチェックしよう」
「アクセスしたあとの動きも、常に見張っておこう」
つまり、ゼロトラストは「疑ってかかる」のではなく、「安全を確認してから許可する」という、ごく自然なセキュリティの進化なのです。
この考え方を取り入れることで、外部からの不正アクセスだけでなく、内部からの情報漏えいや、うっかりミスによるトラブルも防ぎやすくなります。
第3章|ゼロトラストが生まれた背景

ゼロトラストという考え方が注目されるようになったのは、ここ10年ほどの話です。
その理由は、「これまでのセキュリティのやり方では守りきれなくなってきた」からです。
・昔のセキュリティは「お城とお堀」のイメージ
かつての企業では、「社内のネットワークに入っている人=信頼できる人」という前提で守られていました。
たとえば、会社のパソコンからしか業務システムに入れない、社内のWi-Fiにつながっていれば大丈夫、といった感じです。
これは、お城の中に人を入れてしまえば安心、という「お堀」型の守り方に似ています。
でも今の働き方では、その「お堀」の外に社員がいることが当たり前になりました。
・なぜ今、そのやり方では危ないのか?
「テレワークや在宅勤務が増えた」、「社員がカフェや外出先から業務にアクセスする」、「スマホやタブレットで仕事をすることも多い」、「社内のデータをクラウドに置いている」などのような変化により、社内と社外の境界線がほとんど意味を持たなくなっているのです。
さらに、攻撃の手口も巧妙化しています。
見た目では区別のつかない偽メールや、SNS経由のウイルスなど、社員一人のうっかりミスが大きな被害につながることもあります。
・だからこそ「ゼロトラスト」
「誰がどこからアクセスしていても、本当にその人か?安全な状態か?」を確認する。
そんな考え方が必要になってきたのです。
ゼロトラストは、こうした現代の働き方・IT環境に合わせた、今の時代にフィットしたセキュリティモデルなんですね。
第4章|ゼロトラストの基本ルール
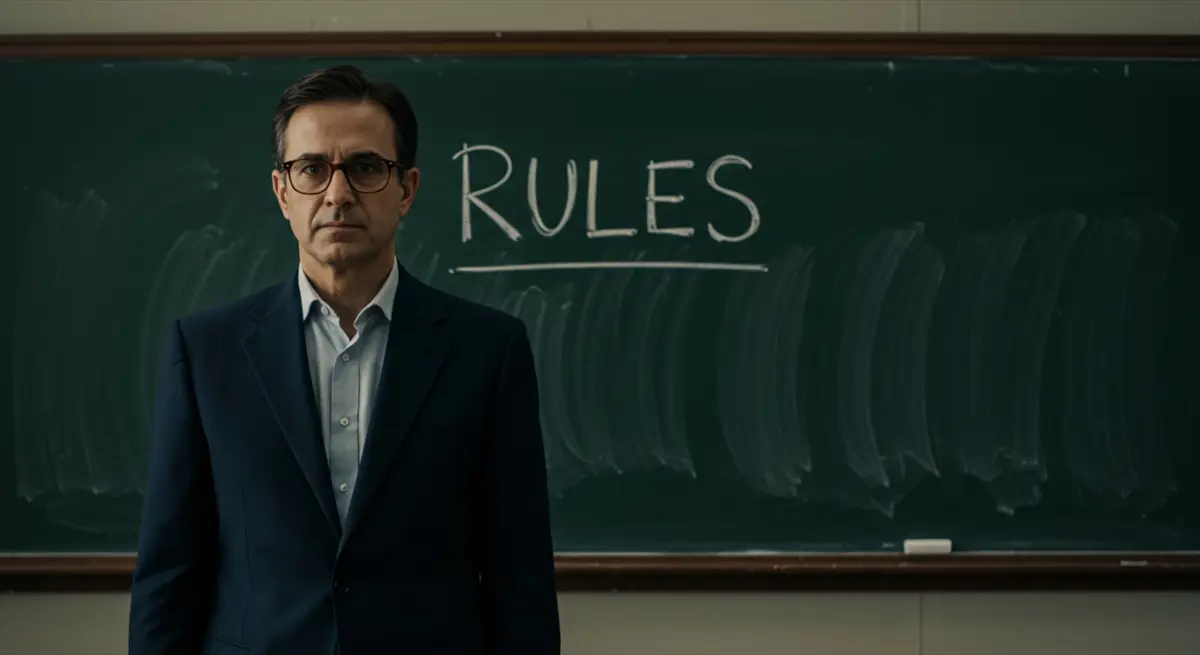
ゼロトラストは、「何も信頼しない」という前提に立ったセキュリティの考え方ですが、その中でも特に大切な3つの基本ルールがあります。
難しく聞こえるかもしれませんが、それぞれとてもシンプルな考え方です。
・常に本人確認
たとえ社内の人であっても、「誰がログインしようとしているのか?」、「使っている端末は登録済みのものか?」、「本当にその人が本人なのか?」など、毎回しっかりと本人確認を行ったうえでアクセスを許可します。
これによって、不正アクセスやなりすましを防ぐことができます。
・必要最低限のアクセスだけ許可
「何でもできる権限」はリスクそのものです。
ゼロトラストでは、業務に必要な最小限の範囲だけアクセスを許可します。
たとえば、新人社員が機密情報にアクセスできる必要はありません。
そういった「本当に必要な人にだけ必要な情報を渡す」ことが基本です。
・監視と記録を常にチェック
アクセスが許可されたあとも、「安心」ではありません。
誰が、いつ、どこにアクセスしたか、その後何をしたのかをしっかり記録しておくことも大切です。
この記録をもとに、不正な行動や、万が一のトラブルの原因を早く見つけることができます。
この3つのルールを守ることで、社内・社外のどこにいても、情報を安全に使える環境が実現できるわけです。
第5章|どんな場面でゼロトラストが役立つのか?

ゼロトラストは、セキュリティを強化するだけでなく、私たちの働き方や学び方を「安全に、そして柔軟に」するための仕組みでもあります。
今の時代、場所やデバイスを選ばずに仕事をしたり学んだりするのが当たり前になってきました。
そんな日常の中で、ゼロトラストがどのように役立っているのか、いくつかの場面を思い浮かべながら見ていきましょう。
まず、多くの人が経験しているであろうテレワークや在宅勤務の場面です。
コロナ禍をきっかけに一気に広がったこの働き方ですが、自宅のWi-Fiや、持ち歩いているノートパソコンなど、以前の「社内限定」の環境に比べて、どうしてもセキュリティ面での不安が増します。
ゼロトラストの考え方を取り入れれば、自宅からアクセスする場合でも、毎回きちんと本人確認が行われ、使っている端末が安全なものかどうかもチェックされます。
そのうえで、仕事に必要な範囲のデータだけにアクセスが許可される。つまり、外にいても、守られた空間で働くことができるのです。
次に、企業や学校で日常的に使われるクラウドサービスの活用シーンです。
ファイルの保存や共有、オンラインでの業務ツールなど、多くの情報がインターネット上に存在する今、誰でもどこからでもアクセスできるという便利さは、同時にリスクにもなります。
ゼロトラストでは、ユーザーの身元、アクセスする場所、使用している端末の状態などを総合的に判断して「このアクセスは許可してもよいか?」を判断します。
たとえ正しいIDとパスワードを使っていたとしても、怪しいアクセスはブロックされるので、安心感がまるで違います。
また、これは意外かもしれませんが、ゼロトラストは教育現場でも大いに役立ちます。
たとえば、学生が自宅のパソコンやスマホから、学校のシステムにアクセスするケースです。
ゼロトラストの考え方が導入されていれば、学生ごとにアクセスできる情報がきちんと制限され、先生の資料や成績データなどの機密情報が守られます。
教職員や外部の講師も同様で、それぞれの役割に応じて必要な情報だけにアクセスできるため、無駄なリスクを減らすことができます。
このようにゼロトラストは、特定の大企業だけの話ではありません。
実は私たちのすぐそばの場面で、静かに、でも確実に「情報を守る役目」を果たしているのです。
第6章|導入する企業はがまず始めること

「ゼロトラストは大切そうだけど、実際どうやって始めればいいの?」
これは、多くの企業や組織が最初に感じる疑問です。
確かに、ゼロトラストというと、すべてを一新する大掛かりなプロジェクトのような印象を持たれるかもしれません。
ですが、実際には、いきなり全部を変える必要はなく、できるところから少しずつ始めるというのが現実的で、多くの企業がそのように取り組んでいます。
まず、多くの企業が着手しているのが、「本人確認の強化」です。
従業員が社内システムやクラウドサービスにログインする際に、多要素認証を取り入れるところから始めます。
これは、パスワードだけでなく、スマートフォンの認証アプリや指紋認証などを組み合わせることで、本人であることをより確実に確認できる仕組みです。
導入のハードルが比較的低く、効果も大きいため、初期のステップとして選ばれやすいのです。
次に見直されるのが、「誰に、どの情報へのアクセスを許すのか?」という権限の整理です。
業務に必要のないファイルやシステムにまでアクセスできる状態は、万が一のときにリスクが広がります。
そこで、役職やチーム、仕事内容に応じて、アクセス範囲をきちんと制限していくこと。
これもゼロトラストの考え方に沿った大切なステップです。
さらに、最近では、社員の端末や通信の状態をリアルタイムでチェックできる仕組みを導入する企業も増えています。
たとえば、「このパソコンはウイルス対策が最新じゃないから、アクセスを一時的にブロックする」といった判断が自動で行われるようになれば、より安全性が高まります。
つまり、ゼロトラストは、いきなり完成させるものではありません。
小さな一歩から始めて、少しずつ広げていくアプローチが、多くの企業で採用されているやり方なのです。
このように、まずは今の状況を見直すことで導入を段階的におこない、「何を守るべきか」、「どこにリスクがあるのか」を整理することから、ゼロトラストは始まっていきます。
第7章|ゼロトラストは難しいもの?誤解されがちなポイント
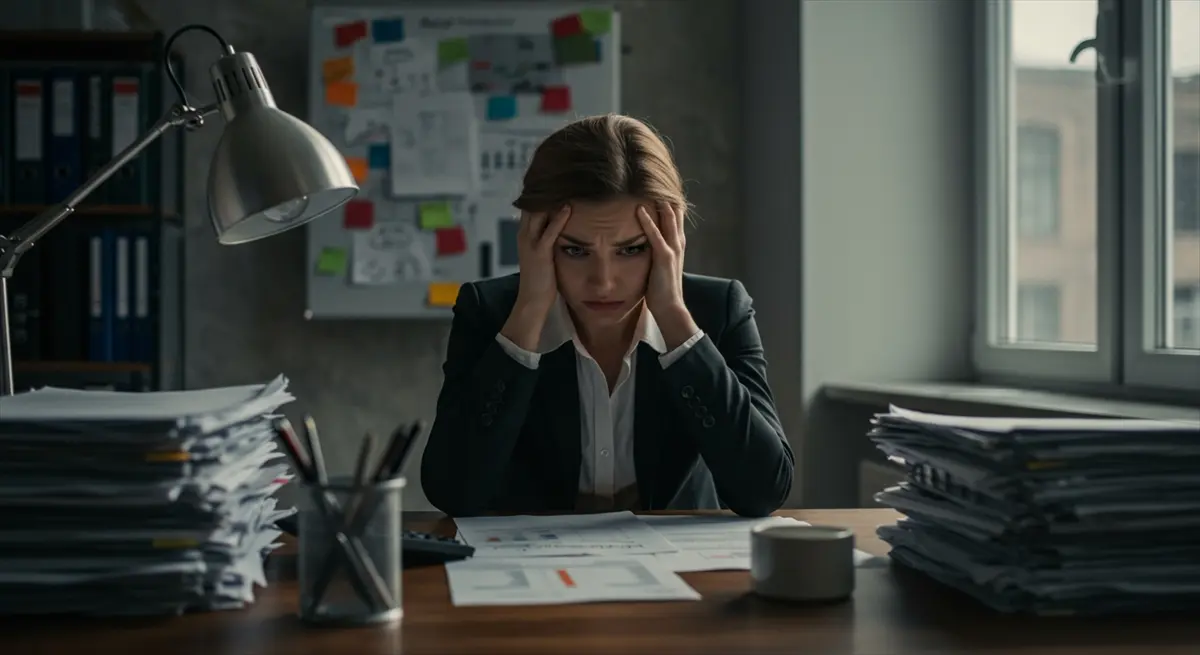
ゼロトラストという言葉を初めて聞いたとき、多くの人がこう思います。
「なんだか難しそうだな」
「うちみたいな中小企業には関係なさそう」
「全部のシステムを一気に変えなきゃいけないの?」
でも実は、そうしたイメージの多くは誤解にすぎません。
ゼロトラストは、最新のテクノロジーや大企業だけのものではなく、今ある環境を少しずつ見直していくための「考え方」や「方針」なんです。
たとえば、すぐにできる取り組みとして、パスワードの見直しや、重要な情報へのアクセスに段階的な確認を加えるだけでも、ゼロトラストの第一歩になります。
よくある誤解のひとつが、「ゼロトラストを導入するには、システムを全部作り変えないといけない」という考えです。
実際には、そんな必要はありません。
今ある仕組みを活かしながら、「どの部分にゼロトラストの考え方を加えていくか」を整理し、できる範囲から取り入れていくのが普通の進め方です。
また、セキュリティ対策は不便になることなどという印象を持たれることもありますが、ゼロトラストはむしろ安全と利便性のバランスを取るための工夫に満ちています。
たとえば一度ログインして信頼された状態であれば、再認証の回数を減らすこともできますし、普段と同じ行動をしていれば何も変わらずに使える仕組みもあります。
つまりゼロトラストは、怖がるものでも、難解な理論でもありません。
「何が起きても情報を守れるように、日々の運用を少しずつ賢くしていこう」という、とても現実的で前向きなセキュリティの考え方なのです。
第8章|これからの時代に必要な「セキュリティの考え方」

ここまでで、「ゼロトラスト」という言葉に少し親しみが湧いてきたのではないでしょうか。
ゼロトラストは、決して特別な人だけが理解すればいい難解な仕組みではありません。
それは、情報を守りながら、私たちがもっと自由に、もっと柔軟に働いたり学んだりできるようにするための、新しいセキュリティの考え方です。
何かを疑うのではなく、「大切なものだから、ちゃんと確認してから使おう」というシンプルな姿勢と、それを、一度きりではなく、毎回ていねいに続けていくことが、ゼロトラストの本質です。
私たちの暮らしや仕事がどんどんオンラインに広がっていく中で、情報の安全はますます重要になっていきます。
だからこそ、「誰かが守ってくれる」ではなく、「自分たちで守る仕組みを持つ」ことが、これからの基本になっていくのです。
ゼロトラストは、その第一歩を踏み出すための、心強い味方になってくれるはずです。
難しく考えすぎず、まずは「今、どこに情報があり、誰がどんなふうに使っているのか?」を見つめ直すところから始めてみましょう。
それが、未来のセキュリティをつくる一歩になります。