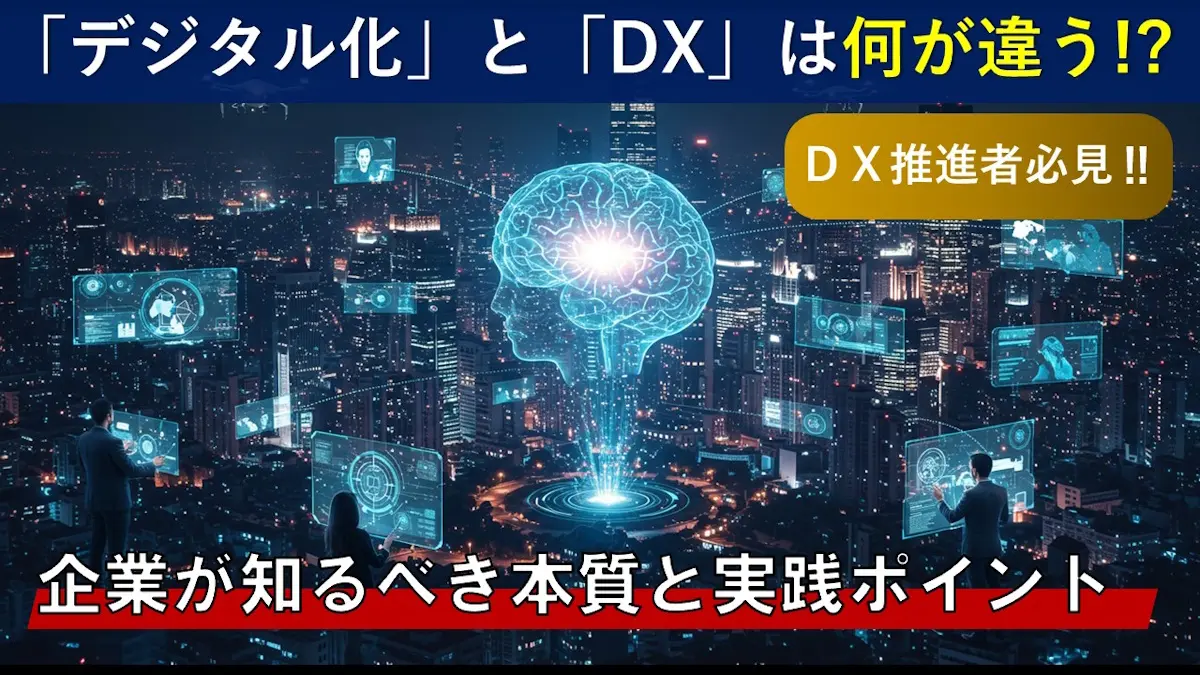
【徹底解説】「デジタル化」と「DX」の違いとは? 企業が知るべき本質と実践ポイントを解説
最終更新日:2025/03/22
皆さんは「デジタル化」と「DX」の違いを理解し、企業活動に応用できていますか?
DX(Digital Transformation)は、データやデジタル技術を活用し、企業のビジネスモデルやプロセスそのものを変革して新たな価値を創出する取り組みです。
一方、デジタル化は既存のアナログ業務をデジタル技術で置き換えることを主眼としており、業務効率の向上や生産性の改善を目的とします。
本記事では、以下の内容を通じてデジタル化とDXの目的や違い、そして両者をどのようにつなげていくかについてより専門的な観点を交えて解説します。
|デジタル化の目的
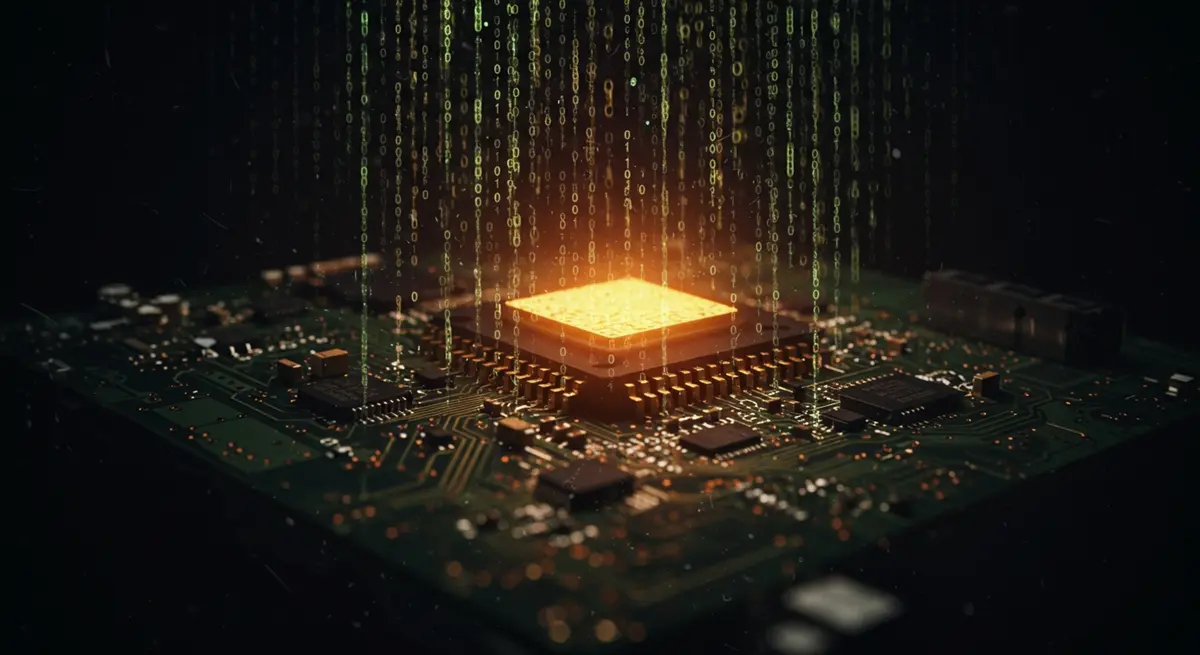
デジタル化の目的は、システムやITツールを活用して業務の負荷軽減や効率性を高めることで、生産性を向上させることにあります。
いわゆる「アナログからデジタルへの転換」(Digitization)や、「既存の業務にITツールを導入して効率化を図る」(Digitalization)の段階が含まれます。
デジタル化の代表的な例として、コミュニケーション手段の進化があります。
過去は電話やFAX、書類の郵送など、アナログな手段が中心でした。これらは時間や場所の制約が大きく、業務効率やスピードに限界がありました。
しかし現在は、電子メールやチャットツール、オンライン会議システムが当たり前となり、離れた場所でもリアルタイムに情報を共有できます。
時間とコストの削減はもちろん、チーム間の連携や意思決定の速度も飛躍的に高まりました。
これらのデジタル化によって、時間や場所にとらわれないコミュニケーションが可能になり、業務効率が高まりました。
さらに昨今では、ビジネスチャットツールやクラウド型業務システムなどを統合的に利用することで、社内外のコラボレーションが一段とスピードアップしています。
また、デジタル化は、「紙の業務をシステム化して終わり」ではなく、徐々に成熟度を高めていくプロセスです。
以下の3ステップで捉えると、今自社がどの段階にあるかがわかりやすくなります。
・段階的導入
ペーパーレス化やSaaSツールの活用、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)の導入といった方法が、最初のステップとして挙げられます。
業務を部分的に自動化・効率化して生産性を上げることを目指します。
・一元管理
次はERP(基幹業務システム)やSCM(サプライチェーン管理システム)、CRM(顧客管理システム)などを連携させることで、情報を一元管理する段階です。
各部門が持っているデータを横断的に扱えるようになり、意思決定の精度が大幅に向上します。
・高度化
データウェアハウス(DWH)やデータレイクを構築し、大規模なデータ分析やリアルタイムモニタリングを行えるようにする段階です。
これにより、予測分析や高度なマーケティング施策など、さらに付加価値の高い活動が可能になります。
|DXの目的

DX(Digital Transformation)は、企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを起点に製品やサービス、ビジネスモデルを変革することに加え、組織・プロセス・企業文化・風土そのものを再構築し、競争優位性を確立することを目的としています。
単なる業務効率化の枠を超えた「ビジネスの再定義」ともいえる活動です。
|DXの具体例

具体例として機械設備メンテナンス事業を行っているA社を例に説明します。
機械設備メンテナンスを行うA社では、「人材不足」と「他社との差別化」を課題として抱えていました。
そこでA社は、IoT技術を活用した計測器や制御器を導入し、ビジネスモデルの変革にチャレンジしました。
・IoT技術による遠隔監視・操作の実現
従来、機械のメンテナンスには、現場に作業員が出向いて点検や操作を行う必要がありました。
しかし、A社が導入した計測器・制御器には、無線デバイスが搭載されており、測定結果を専用サーバーに自動で送信できます。
これにより、作業員が実際に現場へ足を運ばなくても、遠隔で機械の状態監視や制御が可能になりました。
・生み出されたリソースを新サービス開発へ
遠隔監視や操作ができるようになったことで、これまで現場対応に費やしていた作業員の稼働時間を削減できました。
浮いたリソースは、新たなメンテナンスサービスの企画や開発に振り向けられ、結果として新たな収益源を生み出すことに成功。
A社は、単なる業務効率化だけではなく、ビジネスモデルそのものの変革を実現しました。
・A社の学びとポイント
デジタル技術の導入
IoT技術の活用により、遠隔監視や操作が可能に。現場作業が大幅に削減されました。
ビジネスモデルの見直し
人材不足を補うだけでなく、新規サービスを考案することで差別化と収益アップを同時に達成。
データ活用の重要性
計測器が取得するデータを活用し、機械の故障予知やメンテナンスの最適タイミングの算出など、さらなるサービス拡充の可能性を広げています。
A社の事例は、「DX(デジタルトランスフォーメーション)によって競争力を高める」という目的を、IoT技術を活用することで実現した好例といえます。
単なる業務効率化だけでなく、ビジネスのあり方やサービス内容を見直し、新たな収益モデルを築くことがDXの本質ともいえます。
これからIoT技術やデジタル化を検討されている方にとって、A社の取り組みは大きな参考になるのではないでしょうか!?
|DX推進の要素とは?

デジタル化を進めた先にあるDX(デジタルトランスフォーメーション)では、単にITツールを導入するだけでなく、企業活動やビジネスモデルを根本から変革することが求められます。
ここでは、DX推進のために欠かせない3つの要素をご紹介します。
・データドリブンな意思決定
ビッグデータの分析やAIの活用によって、顧客体験や業務プロセスを最適化していくアプローチです。
データを元にした事実ベースの戦略立案は、変化の激しい市場環境でもブレにくい強みになります。
・組織改革・企業文化の変革
DXを成功させるには、経営層から現場社員までがデジタル技術を戦略的に活用できる組織体制や文化をつくる必要があります。
従来の「IT部門だけが担当」という認識を改め、全社的にデジタルリテラシーを底上げすることが鍵です。
・エコシステム構築
自社だけで完結せず、外部パートナーやスタートアップと協力して新しい価値を創り出す取り組みも重要です。
オープンイノベーションなどを通じて、スピード感のある事業立ち上げやサービス開発が可能になります。
|DXの実現に向けてのデジタル化

デジタル化とDXは目的やスコープが異なるものの、段階的には連続しています。
まずは業務をデジタル技術で効率化し、生産性を向上させることでリソースを生み出し、そのリソースを新たな価値創出に振り向けることが重要です。
・デジタル化(Digitization / Digitalization)
ペーパーレス化やRPA、クラウド型SaaSなどの導入。
業務効率化・コスト削減・内部統制の強化。
・データ活用基盤の整備
DWHやBIツール、機械学習基盤の構築。
データの収集・蓄積・分析体制を社内に根付かせる。
・DX(Transformation)
新規事業・サービスモデルの創出、既存ビジネスの抜本的改革。
組織文化・人材育成・外部連携などによる競争力強化。
DXを成功に導くには、従来の業務改革だけでは不十分です。
ステークホルダーやパートナーとの協業体制、社内外のデータを統合的に扱うガバナンス(データガバナンス・セキュリティ)を整備しながら、経営戦略とテクノロジー戦略を連動させることが不可欠です。
|おわりに

DXは「雲をつかむような取り組み」と感じられがちですが、その基盤には着実なデジタル化の推進と、データドリブンな意思決定の仕組みづくりがあります。
自社がどのステージにあるかを認識し、段階的な取り組みを重ねることこそが、最終的にビジネスモデルの変革や競争優位性の確立につながります。
まずは足元の業務をデジタル化しながら、同時にDXにつながるビジョンを描き、経営陣から現場社員までが一丸となって取り組める体制を整えていきましょう。



